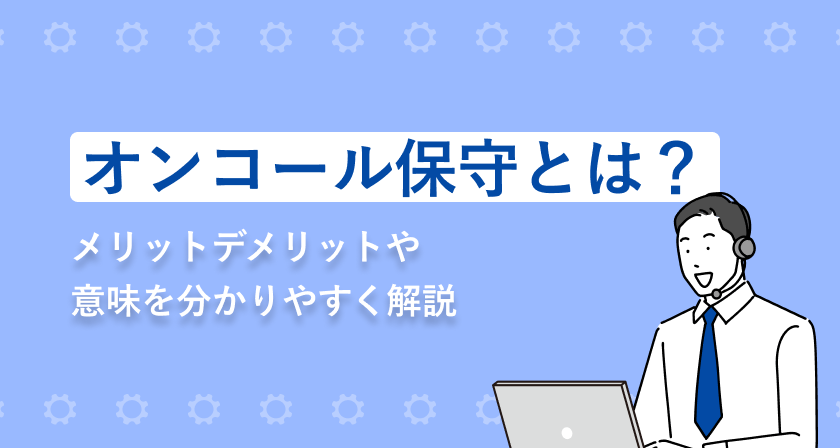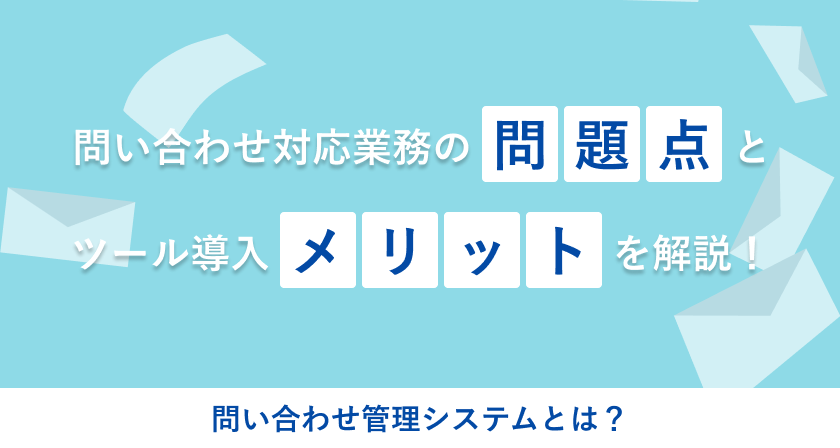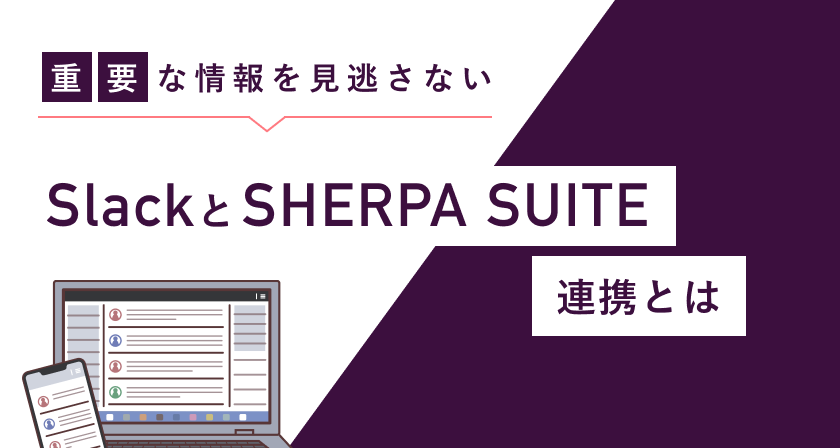オンコール保守とは、システムや機器に問題が発生した際に、契約に基づき対応を依頼する保守形態のことです。
この保守契約は、必要に応じてサービスを受けるスポット契約の一種と言えます。
本記事では、オンコール保守の定義や他の保守形態との違い、メリット・デメリット、そしてどのようなケースに適しているのかを分かりやすく解説します。
オンコール保守の定義
オンコール保守は、IT機器やシステムなどに不具合が発生した場合に、利用者の要請に応じて随時修理やメンテナンスを行うサービス方式を指します。
事前の保守契約を結ばずに、問題が発生した際に都度対応を依頼する有償の保守サービスであり、パーコール保守やスポット保守と呼ばれることもあります。
このサービスでは、対応にかかる作業工数や移動距離などに応じた料金がその都度発生するのが一般的です。

オンコール保守と他の保守契約との違い
オンコール保守と他の保守契約の主な違いは、契約の有無と料金体系にあります。
オンコール保守は、事前の保守契約なしに必要に応じて都度依頼する形式ですが、他の保守契約では年間契約などを締結し、契約期間中は定められた範囲の保守サービスを受けられます。
これらの保守契約は、対象となる機器の使用頻度や重要度に応じて選択することが重要です。
スポット保守との比較
スポット保守はオンコール保守とほぼ同義で使われることが多く、どちらも必要な時にだけ保守対応を依頼するサービス形態です。事前の保守契約は不要で、問題が発生した際にその都度費用を支払います。月々の定額保守料がかからないというメリットがありますが、一度の対応費用は年間保守契約に比べて割高になる傾向があります。特に不具合の発生頻度が高い場合や、迅速な対応が求められる重要なシステムには不向きと言えるでしょう。使用頻度が低い機器や、一時的に使用する機器の保守に適しています。
年間保守契約との比較
年間保守契約は、文字通り年間単位で保守契約を締結する形態です。契約期間中は、定められた範囲の保守サービスを月々または年間の固定料金で受けることができます。オンコール保守のように都度費用が発生するわけではないため、年間の保守費用を一定に抑えやすいというメリットがあります。故障や不具合が発生した場合でも、契約内容によっては回数を気にせずにサポートを受けられます。定期的な点検や部品交換が契約に含まれることも多く、機器を安定稼働させる上で有効な選択肢と言えます。ただし、契約期間中に一度も保守サービスを利用しなかった場合でも費用は発生します。
オンコール保守のメリット
オンコール保守には、いくつかのメリットがあります。必要な時に必要なだけのサービスを受けられるため、コストを抑えられる可能性がある点や、問題発生時に専門家による迅速な対応を期待できる点などが挙げられます。
専門家によるサポートがあるため高度な対応も可能
オンコール保守では、IT機器やシステムに関する専門知識を持った技術者によるサポートを受けられます。これにより、自社内では対応が難しい高度なトラブルや複雑な不具合に対しても、専門的な知識と技術に基づいた適切な対応が期待できます。特に、最新の機器や複雑なシステムを導入している場合、専門家によるサポートはシステムの安定稼働に不可欠と言えるでしょう。問題の根本原因の特定や、より効果的な解決策の提案など、質の高いサービスを受けられる可能性があります。
従業員の負担を軽減できる
システムや機器のトラブルが発生した場合、社内のIT担当者や兼任の従業員が対応に追われることがあります。特に緊急度の高いトラブルの場合、本来の業務から離れて復旧作業を行う必要があり、従業員の負担が大きくなります。オンコール保守を利用することで、トラブル対応の専門家を外部に依頼できるため、社内リソースをコア業務に集中させることが可能になります。これにより、従業員の残業時間削減や、業務効率の向上に繋がるでしょう。

オンコール保守のデメリット
オンコール保守はメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。費用が予測しにくい点や、対応に時間がかかる可能性などが挙げられます。
エラー・不具合の対象に遅れ解消までに時間がかかりやすい
オンコール保守は問題発生時に都度依頼するため、年間保守契約のように事前に対応体制が確保されているわけではありません。そのため、問い合わせから業者の手配、現場への到着、そして修理や復旧作業という流れになり、問題解消までに時間を要する場合があります。特に、営業時間外や休日、または対応拠点が遠方にある場合など、迅速な駆けつけが難しい状況では、システム停止時間が長引くリスクがあります。業務への影響が大きいシステムの場合、この時間的な遅延は大きなデメリットとなり得ます。
費用が高額になるケースがある
オンコール保守は利用する都度費用が発生するため、不具合の発生頻度が高い場合や、一度の対応に時間や部品代が多くかかる場合などには、結果的に年間保守契約よりも費用が高額になる可能性があります。特に予期せぬトラブルが連続して発生したり、広範囲にわたるシステムの復旧が必要になったりした場合など、突発的な出費が増えることで予算管理が難しくなることも考えられます。長期的な視点で見ると、安定したコストで手厚いサポートを受けられる年間保守契約の方が経済的であるケースも少なくありません。
オンコール保守が適しているケース
オンコール保守は、システムや機器の使用頻度が低い場合や、ミッションクリティカルではないシステムに適していると言えます。例えば、たまにしか稼働しない機器や、業務への影響が限定的なシステムであれば、常に手厚い保守契約を結んでおく必要性は低いかもしれません。また、導入したばかりでトラブルの発生頻度が未知数なシステムや、短期間だけ使用するシステムなどにも適しています。さらに、突発的な予算確保が可能で、月々の固定費を抑えたいという企業にも選択肢となり得ます。ただし、一点物の特注システムや古いシステムなど、対応できる業者が限られる場合は注意が必要です。
オンコール対応時の注意点
オンコール対応を依頼する際には、いくつかの注意点があります。まず、事前にサービス提供範囲や料金体系をしっかりと確認しておくことが重要です。どのようなトラブルに対応してもらえるのか、対応時間や料金が発生する基準などを明確にしておく必要があります。また、緊急時にスムーズに連絡が取れる体制を構築しておくこと、そして問題発生時には状況を正確に伝えられるよう、必要な情報を整理しておくことも大切です。さらに、対応後の報告や再発防止策についても確認し、将来的なトラブルの低減に繋げることが望ましいでしょう。待機中の従業員がいる場合は、行動制限に関するルールを明確にし、心身の負担にも配慮する必要があります。
保守の種類
保守契約には様々な種類があり、それぞれ目的や内容が異なります。大きく分けると、問題が発生する前に行う予防保守と、問題発生後に行う事後保守があります。また、ハードウェアだけでなくソフトウェアに対する保守も重要です。これらの保守の種類を理解し、自社のシステムや機器、そしてビジネスの特性に合わせて適切な保守契約を選択することが、システムの安定稼働とビジネス継続のために不可欠です。
予防保守
予防保守は、システムや機器にトラブルや不具合が発生する前に、計画的に実施される保守活動です。その目的は、潜在的な問題点を発見・修正し、将来的な故障やシステム停止を未然に防ぐことにあります。具体的には、定期的な点検、部品の交換、クリーニング、システムの監視などが含まれます。これにより、システムの安定稼働を維持し、予期せぬダウンタイムによるビジネスへの影響を最小限に抑えることが可能となります。日常保守や定期保守といった形態があり、計画的な実施によって長期的な運用コストの削減にも繋がる可能性があります。
事後保守
事後保守は、システムや機器に実際にトラブルや不具合が発生した際に実施される保守活動です。故障箇所の特定、修理、部品交換、データの復旧など、システムを正常な状態に戻すための作業が中心となります。緊急度に応じて臨時保守や緊急保守といった対応が取られることもあります。事後保守は、問題発生後の対応となるため、システムが一時的に利用できなくなるダウンタイムが発生するリスクが伴います。迅速な対応が求められますが、原因究明や復旧に時間がかかる場合もあり、ビジネスへの影響が大きくなる可能性も考慮しておく必要があります。
ソフトウェア保守
ソフトウェア保守は、ハードウェアだけでなく、システムを構成するソフトウェアに対する保守活動です。これには、ソフトウェアのバグ修正(是正保守)、OSや関連ソフトウェアのバージョンアップへの対応(適応保守)、機能改善や性能向上(完全化保守)、そして将来的な障害発生を防ぐための潜在的な問題点の修正(予防保守)などが含まれます。ソフトウェアは常に変化する環境や利用状況に影響を受けるため、継続的な保守が不可欠です。適切なソフトウェア保守を行うことで、セキュリティリスクの低減、システムの安定性向上、そして最新の機能や性能を維持することができます。

オンコール対応時に発生する記録漏れや引き継ぎミスに悩まされている方は、Redmineと連携して対応履歴を自動で可視化できる「SHERPA SUITE」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
突発的な障害対応においても、チーム間でスムーズな連携が取れる体制づくりが求められます。
シェルパスイートは、Redmineと連携しながら、オンコール時の対応ログや通知、エスカレーションの一元管理を実現できます。
夜間や休日の対応が発生した際、どのような対応がなされたのかを記録し、ナレッジとして蓄積する仕組みが整っていない場合、保守品質のバラつきが課題になります。そうした状況を改善したい企業には、「SHERPA SUITE」のRedmine連携機能が効果的です。
属人的になりがちなオンコール対応の記録や工数管理を見直すことで、保守体制全体の品質を底上げできます。Redmineと連携し、保守業務の見える化・自動集計を実現できる「SHERPA SUITE」の導入をぜひご検討ください。
オンコール対応の履歴をRedmineで記録している企業でも、集計や可視化に課題を感じているケースは少なくありません。シェルパスイートなら、そうした対応履歴を自動で整理・集約し、次回対応のナレッジとして活用することが可能です。
万全なオンコール保守体制を築くためには、ただ記録を残すだけでなく、対応内容を正確に蓄積し、共有・分析できる環境が必要です。Redmineと連携した「SHERPA SUITE」は、その実現を強力にサポートします。
SHERPA SUITEはこちら
まとめ
オンコール保守は、システムや機器に不具合が発生した際に都度対応を依頼する保守形態であり、必要な時にサービスを受けられる柔軟性が特徴です。スポット保守やパーコール保守とも呼ばれ、事前の保守契約なしに利用できるため、使用頻度の低い機器や緊急度の低いトラブルに適しています。専門家による高度なサポートを受けられ、従業員の負担を軽減できるメリットがある一方、エラーや不具合の解消に時間がかかったり、利用頻度や内容によっては費用が高額になる可能性があるというデメリットも存在します。自社のシステム環境や予算、そして求められる対応スピードを考慮し、年間保守契約など他の保守形態と比較検討することが重要です。予防保守や事後保守、ソフトウェア保守など、様々な保守の種類を理解した上で、最適な保守体制を構築することが、システムの安定稼働とビジネス継続の鍵となります。